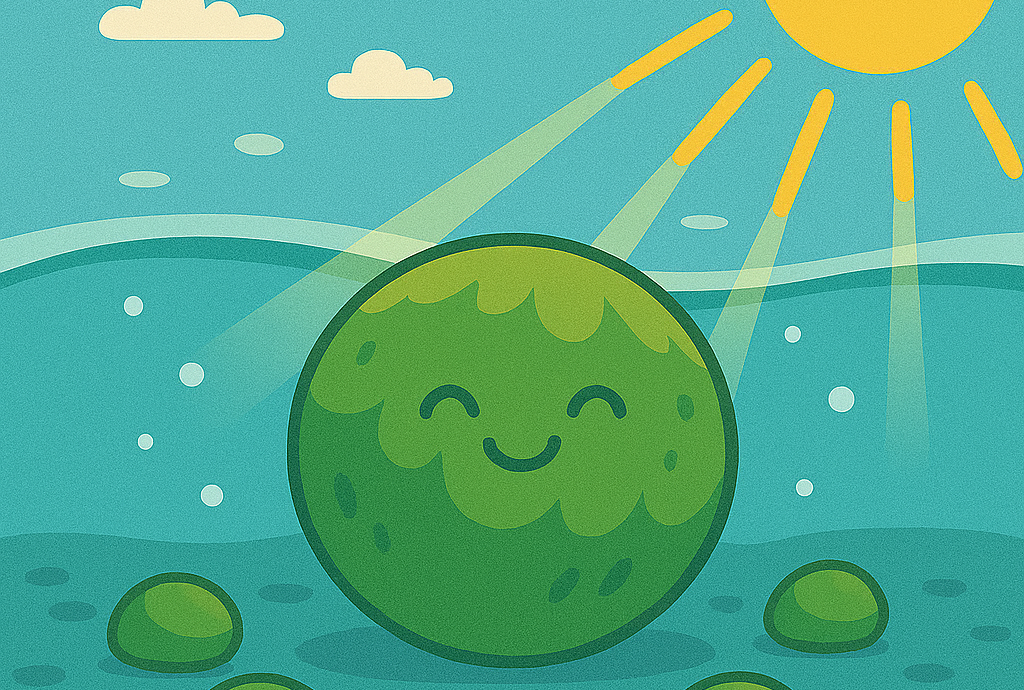北海道の阿寒湖には、世界でも珍しい丸いマリモが多く生息しています。
マリモは、太陽の光を利用して栄養をつくる「光合成」を行いながら生きています。
マリモの生息地である阿寒湖は、冬になると厚い氷と雪に覆われ、強い日差しからマリモを守る「日傘」のような役割を果たします。
春になると氷が溶けますが、水温はまだ低いため、冷たい水の中で強い光を浴びたマリモは「光阻害」というダメージを受けます。
強すぎる太陽の光は、光合成をする植物に良くありません。光阻害とは、強い光によって光合成の働きが妨げられ、栄養をうまく作れなくなる現象です。
ダメージを受けたマリモの元気度を示す指標(Fv/Fm)を調べると、健康な状態では約0.6ある数値が、約0.27にまで低下していました。
しかし、マリモには高い回復力があることもわかりました。
ダメージを受けてから20~30日ほど経ち、水温が上昇する頃には、光合成の力が回復し、元気な状態(約0.55)まで戻ることが確認されました。
この研究で、マリモが最も弱い時期が特定されました。
地球温暖化で氷が早く溶けると、マリモが冷たい水の中で強い光にさらされる期間が長くなり、ダメージを受ける期間が長くなる恐れがあります。
春先の環境変化に注目し、マリモを守ることが大切です。
☑️マリモ
マリモは、池や湖などの淡水に住む緑色の藻の仲間です。
マリモの本当の体は細い糸のような形(糸状体)をしていますが、風や波の力で湖の底をコロコロ転がることで、この糸が集まり丸いボールの形になります。
北海道にある阿寒湖のマリモは、直径30cmにもなる大きな球状に育つため、特別天然記念物として大切に守られています。水中で光合成をして成長します。
☑️地球温暖化
地球温暖化は、私たちが電気や車などで石油や石炭を使うときに、二酸化炭素(温室効果ガス)が大量に出すぎて、地球の熱が宇宙に逃げられなくなる現象です。
このガスが増えると、地球の温度がどんどん上がり、台風や大雨などの激しい異常気象が増えたり、海面が上がって低い土地が沈んだりする影響が出ます。このため、世界中の国々が協力し、二酸化炭素を減らすために取り組んでいます。
●参照元:
氷の下で眠るマリモ:春の光がもたらす危機と回復 自然科学研究機構 アストロバイオロジーセンター